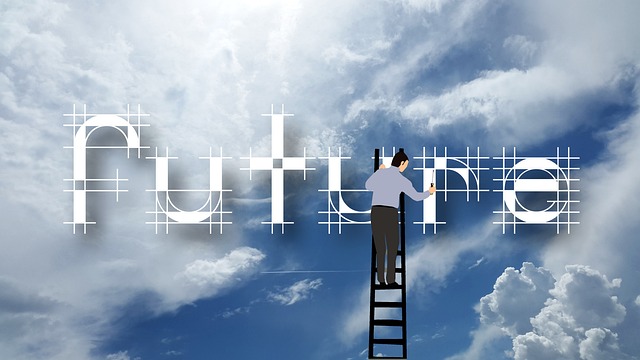
デジタル庁への「提言」と言うと大げさに聞こえるかもしれません。
しかし、デジタル化の本来の目的は「個別最適」ではなく「全体最適」。つまり、デジタルの民主化です。各企業が独自の仕組みを運用していては限界があり、社会全体としてのDXを進めるには、横串での最適化が不可欠です。
その意味で、「まちの総務」の立場から声を上げることには意義があると考えています。
SaaS普及の功績と限界
クラウドを活用したSaaSアプリの普及により、従来の高額な独自システムが不要になり、アプリの民主化は大きく進みました。
しかしその一方で、現在はSaaSが乱立し、システム間のデータ連携が不十分という課題が顕在化しています。
現状、多くはCSVでのデータ受け渡しに頼り、同一ベンダーの製品群であれば連携可能ですが、異なるベンダー間では共有が難しいのが実態です。これではクラウド本来のメリットを十分に活かし切れていません。
SaaS連携が進まない理由
課題の背景には「データの標準化(コード体系)」がメーカー任せであることがあります。
各SaaSはあくまで自社内の業務完結を目的に設計されており、二次利用は二の次。囲い込み戦略の一環として、異なるサービス間のデータ連携が後回しにされてきたのです。
結果として、たとえば人事・給与・勤怠など複数のSaaSを利用する総務部門でも、情報の一元管理が難しい状況が生まれています。
必要なのは「標準化」と「旗振り役」
この状況を打破するには、SaaS間のWebAPI連携を標準化する仕組みが欠かせません。
技術的には既存の仕組みで十分に実現可能ですが、問題はそれを取りまとめる組織やリーダーシップの不在です。
すでに地方自治体向けに基幹業務システムの統一・標準化を進める動きが始まっています。ここから民間へと展開していくことを、デジタル庁に強く期待したいところです。
標準化団体や外郭組織を通じて、クラウド「過渡期」を越え、真の「恩恵期」へと進めるかが問われています。
まとめ:DXの推進力は「つながる仕組み」にあり
SaaSは便利さをもたらしましたが、それだけでは十分ではありません。
今後のDXを支えるのは「つながる仕組み」すなわちAPI連携の標準化です。
- 企業間商取引の汎用化と中小企業版JANコード化
- 個別会計処理の統合化
- 個別給与計算の統合化
- 企業提出情報のDB化(紙の電子化NG)
- 番外編:SaaS情報のWebAPI連携の標準化 ⇦ 今ここ
- 番外編:情報セキュリティ管理は独自運用では無い
これらはいずれも「まちの総務」的視点から見た、社会全体のDX推進に不可欠なテーマです。
今後もデジタル庁の取り組みに注目しつつ、現場の声として提言を続けていきたいと思います。
「レッツDX!」

