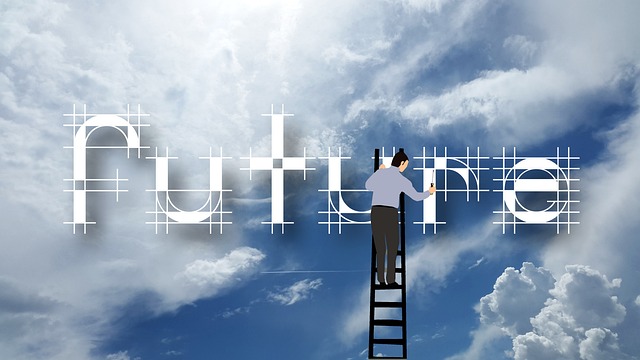
デジタル庁への「提言」と言うと大げさに聞こえるかもしれません。しかし、デジタル化の最大の目的は「個別最適」ではなく「全体最適」、すなわち“デジタルの民主化”にあると私は考えています。各企業が独自に運用する仕組みには限界があり、だからこそ「まちの総務」として全体最適の視点から提言することには意味があると信じています。
前回は「企業間商取引の汎用化と中小企業版JANコード化」として、コードの標準体系化や汎用ECサイト構想について触れました。今回は、その続編として「個別会計処理の統合化」に関する考えをお伝えします。
なぜ企業が自前で会計処理をしなければならないのか?
まず大前提として「企業が収益をまとめ、国に税金を納めること」は義務です。税金は最終的に国民へ還元されるものですが、整理してみると以下のような構図になります。
- 税金を支払う側:企業(納税者)
- 税金を徴収する側:国(受給者)
ところが現状では、支払う側である企業が、自らの会計システムや会計事務所を通じて手間とコストをかけて申告を行っています。制度に合わせるために、納税者側がここまで負担を背負う仕組みは、少々「横柄」ではないでしょうか。
国が制度を作り、最終的に税金を確定させるのであれば、その過程の仕組みも国が責任を持って用意するのが筋のはずです。
国主導の標準会計システムの必要性
中小企業にとって、個別の会計ソフト導入や税理士費用は大きな負担です。国が提供する統一的かつ汎用的な仕組みがあれば十分なはずです。実際、デジタル大臣も「年末調整を廃止し、全納税者が確定申告する案」を示しており、その流れの中で会計処理の統合化は現実味を帯びています。
現行の「e-TAX」は、あくまで申請データを確定した後に登録する仕組みにとどまっています。本来は、マネーフォワードやfreeeといったサービスが担っている「申請前の入力・処理」までを国が無償提供するのが理想です。
クラウド上に集めた取引データを自動仕分けし、税額を自動計算する仕組みが整えば、中小企業は最小限の入力で納税が完結できます。領収書も紙ではなく、クレジットカードやデジタル決済による電子履歴が増え、オンラインでの管理はますます容易になるでしょう。
統合化で見える未来──AIによる自動会計処理へ
過去の会計データがクラウド上で一元管理されれば、AIによる自動計算・自動申告も視野に入ります。大きな変化がなければ、年末調整もほぼ自動で完結できるようになるはずです。
一方で、現状では会計情報の長期保管義務や、補助金・助成金の申請時に既に登録済みのデータを再提出させられるなど、非効率が目立ちます。こうした「縦割り行政の壁」を打破し、制度やデータ管理を横断的に統合できるのは、まさにデジタル庁の役割です。
提案──「標準会計システム」の国主導での提供を
具体的には、現在各社が導入しているマネーフォワード・freee・弥生会計などの仕組みを統合化し、ガバメントクラウドとして標準版を提供することを提案します。
- 1から開発するのではなく、既存システムを統合・買取・格安提供する
- 最終結果だけでなく、過程データも記録できるようにする
- 制度変更にも柔軟に対応可能な仕組みとする
こうした取り組みによって、会計事務所の役割を否定する必要もありません。あくまで「最低限の会計処理を誰でも安心して行える環境」を国が提供するべきなのです。
DXの本丸は「会計処理の消滅」
最終的には「会計処理そのものが不要になる」ことが、DXによる最適化の本丸となるでしょう。会計情報がデジタルで自動収集・処理され、納税がシームレスに完結する未来です。
その第一歩が「会計処理システムの国主導による統合化」であり、中小企業の負担軽減にも直結します。デジタル庁には、ぜひこの分野でのリーダーシップを期待したいと思います。
「レッツDX!」

