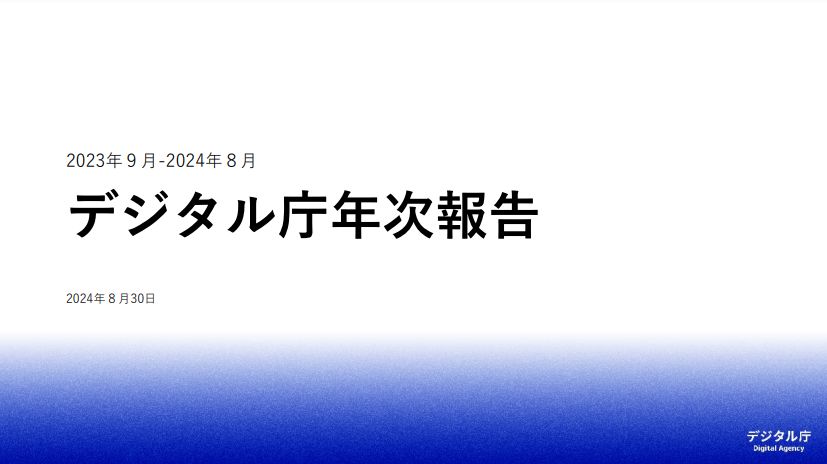
「まちの総務」として日々、企業のデジタル推進を支援している立場から見ると
「デジタル庁」という存在は非常に象徴的です。
なぜなら、その歩みや課題は、多くの企業が抱える“デジタル化の現実”をそのまま映し出しているからです。
■ 企業も行政も、それぞれの“個別最適”が生んだデジタル格差
これまで日本の企業や行政機関は、業務の合理化を目指してそれぞれが独自にデジタル化を進めてきました。
しかし、部門ごと・組織ごとに異なる仕組みやルールが乱立した結果、全体最適からは程遠い
「個別最適の集合体」となり、結果的にデジタル格差が広がってしまったのです。
規模の大きな企業や自治体はシステム投資によって先行できる一方
中小企業や地方自治体はリソース不足から取り残されがち。
この構図こそが、今の日本社会全体における「デジタルの遅れ」の根本原因といえるでしょう。
■ デジタル庁という“異色の省庁”の誕生
本来、政治の中心的なテーマといえば「経済」「社会保障」「外交・安全保障」の三本柱。
国民の生活に直接関わる領域ではあるものの、日常感覚からはやや遠い議論が続いてきました。
そこに誕生したのが「デジタル庁」です。
これは、国民一人ひとりの暮らしに密接に関わる、省庁としては珍しい“生活直結型の組織”といえます。
行政のデジタル化を通じて「国全体の生産性を高める」という目的は明快ですが
実際の施策が発表されるたびに
「時期尚早だ」「強引すぎる」「現場が追いつかない」といった批判が噴出します。
興味深いのは、この光景がまさに企業内のDX推進現場と重なることです。
■ 「デジタル推進派」と「反デジタル派」の攻防はどこでも同じ
社内で新しいデジタルツールを導入しようとすれば、
「今のままで十分」「これ以上は現場が混乱する」といった反対意見が必ず出てきます。
一方で、「業務効率化や標準化は避けて通れない」と考える推進派もいる。
この二つの立場がせめぎ合う構図は、国レベルでも企業レベルでも変わりません。
押し切って進める組織は成果を上げ、
反発が強くブレーキがかかる組織は、結果としてデジタル化が遅れます。
「デジタル庁の苦労」は、まさに私たち企業人の姿そのものなのです。
■ デジタル後進国からの脱却に向けて
日本は長らく「デジタル後進国」と呼ばれてきました。
その要因の一つは、ITそのものの問題ではなく、「標準化」や「ガバナンス」に対する文化的な遅れにあります。
しかし今、行政も企業も少しずつ“全体最適”を意識し始めています。
バラバラなシステムを連携させ、国民や利用者の利便性を第一に考える仕組みを整えようという動きが
確実に広がっています。
「デジタル庁年次報告」にも、その努力の軌跡が示されています。
(参考リンク:デジタル庁 年次報告書)
■ まとめ:デジタル庁を“批評”ではなく“教科書”として見る
デジタル庁の取り組みを、単なる政策論や失敗談として眺めるのは簡単です。
しかし視点を変えれば、そこには企業DXに通じる多くの学びがあります。
組織の壁、現場の抵抗、スピード感のずれ。
それらをいかに乗り越えるかを考える上で、「デジタル庁の歩み」は私たちに多くの示唆を与えてくれるはずです。

