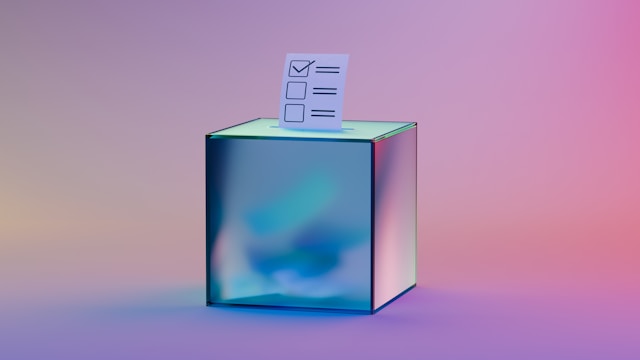
近年、選挙活動のあり方が大きく変わりつつあります。
これまで「オールドメディア vs ネット」という二項対立で語られることが多かった選挙報道ですが
今注目すべきは、その枠を超えて“これまで政治に無関心だった層”が動き出している点です。
若年層の「無関心」が揺らぎ始めた理由
投票率向上を目的に、これまで多くの施策が試みられてきました。
しかし、若者を中心とする「政治への無関心」は根強く
「日本は平和だから政治に関心を持たなくても大丈夫」という空気が長く続いてきました。
他国では社会不安が政治参加を促す要因となるのに対し
日本ではその“平穏さ”が関心の低下を生んでいるのです。
かくいう私自身も、これまで選挙には欠かさず参加してきたものの
「自分の一票で何も変わらない」という無力感を抱いていました。
しかし、2024年以降の、一連の選挙活動では、明らかにこれまでとは異なる動きを感じました。
ネットがもたらす“新しい選挙活動”の形
「ネット選挙」という言葉は以前から議論されていますが
法整備やセキュリティ、インフラの格差、本人認証など、実現にはまだ多くの課題があります。
それでも注目すべきは、ネットが「システム」ではなく「手段」として
すでに選挙活動のあり方を変え始めているという事実です。
たとえば次のような変化が見られます。
- スポンサー忖度の可視化
オールドメディアによる偏向報道が、ネット上で検証・指摘される機会が増えました。 - 情報の非対称性の崩壊
かつては情報を持つ組織が圧倒的に有利でしたが、ネットの普及により
誰もが発信・検証できる環境が整いました。 - “無関心層”の可視化と感情の共有
これまで沈黙していた人々の不満や意見が、SNSを通じて一気に表面化しています。
こうした変化は、単に「ネットがメディアを凌駕した」という単純な話ではありません。
むしろ、根拠のない情報が拡散するリスクも依然として存在します。
それでも、ネットが「民意を可視化し、行動を促す力」を持つことは、もはや疑いようがありません。
「自分たちで世の中を動かせる」という感覚の芽生え
今回の選挙活動で最も注目すべき変化は、人々の意識そのものです。
ネットを介して、「自分たちの意志で社会を変えられる」という実感が広がりつつあります。
かつては、自分の住む地域以外の首長選挙に関心を持つ人はほとんどいませんでした。
それが今では、全国の選挙結果をリアルタイムで追い、自分ごとのように感じる人が増えています。
この“意識の変化”こそ、まさにDX(デジタルトランスフォーメーション)の一側面といえるでしょう。
DXが描く「選挙の未来」
2024年以降の選挙は、後世において「時代の転換点」として語られるかもしれません。
ネットの力が、これまで緩やかにしか動かなかった政治構造に対し、劇的な変化をもたらしました。
この潮流は、政党間の力関係のみならず、地方政治のあり方にまで波及していく可能性があります。
デジタル技術が人々の意識と行動を変え始めたこの現象こそ
「DXの真髄」と呼ぶにふさわしいのではないでしょうか。
ネットがもたらす政治のDX、その次の展開から、ますます目が離せません。

