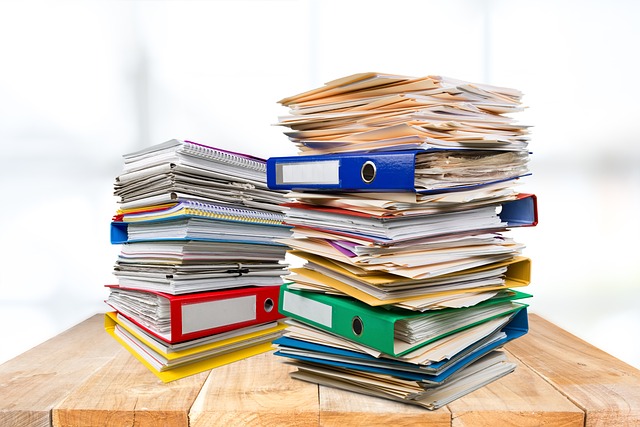
現場で実際に起きている課題を、DXの視点から読み解くシリーズです。
今回取り上げるのは、「勤怠管理から給与計算に至るプロセスにおける非効率さ」について。
企業規模や業種を問わず、どの会社でも必ず行われているのが「勤怠管理」と「給与計算」。
支払うべき給与(アウトプット)は同じにもかかわらず、そこに至るまでの情報(インプット)が企業によって異なるために、業務が煩雑化し、統合や効率化が進まないという実情があります。
なぜ勤怠〜給与計算プロセスの統合は難しいのか?
たとえば、給与形態は企業や職種によって、年俸制、月給制、週給、日給、時給とさまざまです。
しかし、最終的には「働いた対価として報酬を支払う」という結果(アウトプット)は共通です。
にもかかわらず、勤怠管理の手段がバラバラであるために、処理の方法も企業ごとに千差万別。
ある企業では手作業で勤怠データを入力していたり、別の企業ではクラウド型の勤怠システムを使っていたりと、インプットの形式が統一されていません。
その結果、企業ごとに担当者を配置し、毎月、締切とミスのプレッシャーと戦いながら、同じような作業を繰り返しています。
DXの視点で見る“勤怠管理〜給与計算”の非効率構造
そもそも「給与」とは、働いたことへの対価として支払われる報酬です。
それが「時間の束縛」や「成果」によって評価され、金額に換算されるのが基本的な仕組みです。
この構造は、昭和の時代からほとんど変わっていません。
しかし、DXの観点から見ると、こうした旧来型のプロセスは改善されずに残っている非効率の温床とも言えます。
特に小規模企業で目立つ“仕組みの乱立”
大手企業や中堅企業では、システム導入によって業務の標準化・効率化がある程度進んでいます。
一方で、小規模企業に目を向けると、以下のように仕組みがバラバラであるケースが目立ちます。
- 情報の収集方法: Web勤怠管理/タイムカード/紙の台帳
- 情報の集計方法: 自動集計システム/Excelによる手入力集計/電卓による手計算
これらは、企業ごとの歴史や経営者のこだわり、就労条件の違いなどが複雑に絡み合って、現状のまま継続されていることが多いのです。
では、DXによる変革はどう進めるべきか?
「企業ごとの事情が違うから、統一化は無理だろう」
そう感じる方もいるかもしれませんが、こここそがDXによる変革の入り口です。
まず問いかけたいのは、「そもそも、業務を効率化したいと思っていますか?」という基本的な姿勢です。
「昔からこのやり方でやっているから、変える必要はない」という方には、無理に改革を押しつけることはできません。
一方で、「今のやり方を何とかしたいが、どうすればいいのか分からない」という方。
こうした方々と一緒に、変化への一歩を踏み出す議論を進めたいと考えています。
ポイントは“変化を受け入れる姿勢”
「結果が同じなら、やり方が変わっても構わない」
こうした柔軟な考え方があるかどうかが、DX推進の鍵になります。
もし、「従来のやり方に強くこだわる」という状況であれば、無理に変えるのではなく、いったん保留にしておくのも一つの選択です。
一方で、「変化は厭わない」と考える方とは、よりよい業務プロセスを共に設計していくことが可能です。
この議論をさらに深めるために、DXの視点からその可能性を探っていきます。

