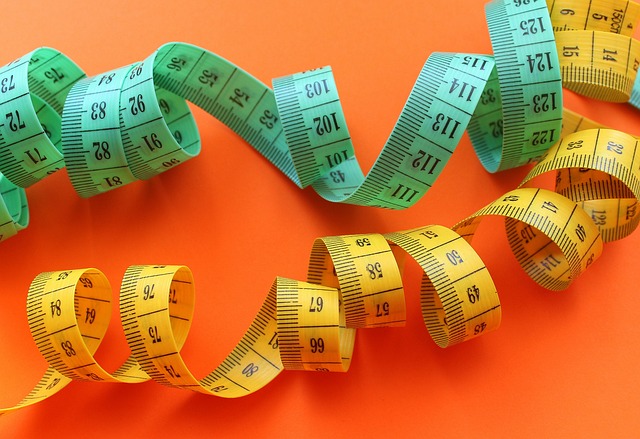
前回のコラムでは、バックオフィス業務を標準化する過程で浮き彫りになる「ExcelマクロやRPAの属人化・継承性」の課題についてご紹介しました。これは、1社の中で完結してしまう仕組みによく見られる問題です。
こうした課題は、良い仕組みを他社にも展開し、広く共有していくことで解決できます。もし必要があれば、私たちがマニュアルや仕様書の作成をサポートすることも可能です。
標準化の次のステップ:「良い仕組みをどう広げるか?」
業務の標準化が整った後に訪れる次の課題は、「その仕組みをどう広げていくか?」という点です。どれだけ優れた仕組みであっても、“知ってもらい、使ってもらう”ことがなければ、何も始まりません。
現代はSNSやWebを通じて情報発信がしやすくなった一方で、本当に使ってもらえる仕組みを広く認知してもらうのは容易ではありません。待っているだけで“自然にバズる”ことはまずありません。
中小企業が取るべき現実的なアプローチ
大企業や広報予算が潤沢な企業であればCMなどの手段も取れるでしょう。しかし、私たちのような中小企業や地域企業が選ぶべき現実的な手段は、地道ではあるが効果的な「事例ベースの拡散」です。
【Step 1】身近な企業での試用とフィードバック
まずは信頼関係のある企業に試用してもらい、評価や改善点を集めましょう。
【Step 2】地域団体や業界団体への働きかけ
次に、地域の商工会や業界団体(例:◯◯協会、◯◯組合)などへアプローチをかけます。この際、Step1で協力してくれた企業の経営者の紹介が大きな力になります。
【Step 3】クチコミとコンテンツ発信の併用
徐々に利用者の声が広がるのを待ちつつ、ブログやSNSを通じて活用事例を発信していきます。このタイミングで、経済誌や新聞社などのメディアへの情報提供も視野に入れます。
想定すべき「バズった場合」の次の一手
万が一、大きな注目を集めた場合の備えも必要です。1社だけで対応しきれないケースも考えられますし、サポート体制には限界があります。
そこで次に考えるべきは、ユーザーコミュニティの立ち上げです。
SlackやChatwork、Discordなど、ツールは問いません。ユーザー同士が質問・回答・アイデアを共有できるオンラインコミュニティを構築し、情報の循環を自律的に生み出す仕組みを作りましょう。
私たち「まちの総務」は、サポート役というよりは“場づくりの担い手”です。この場を通じて、ユーザー自身が仕組みを育てていく。それこそが理想の姿です。
まずは5社から、自然増へ
最初は5社。そこから10社、20社へと少しずつ広がり、やがて自然に広がっていく――そんな未来を描いています。
多くの企業担当者はSNSを積極的に使うわけではありませんが、クローズドで信頼性の高い業務特化型コミュニティであれば、心理的なハードルも下がるはずです。
もちろん、まずはユーザーに「使ってみたい」と思ってもらえるコンテンツ作りが最優先です。そして、広く展開する前に、特定の業種にフォーカスして深掘りすることが重要です。
今が、その「素地づくり」のフェーズ
ありがたいことに、すでに数社の協力的な経営者や、アイデア豊富な担当者が支援してくださっています。こうした仲間とともに、小さな仕組みを実験的に形にしていく――まさにミニプロジェクトの始まりです。
通常業務とは異なる視点で、未来志向の取り組みを始めてみませんか?きっと日常業務にも新しい刺激と“ワクワク”が生まれるはずです。
最後に──
「Pay it forward(恩送り)」の精神で、共に未来をつくりましょう
誰かに受けた親切や恩を、次の誰かに送る。「恩返し」ではなく、「恩送り」を。
そんな価値の連鎖が、地域の企業の可能性をさらに広げていくと私たちは信じています。
まちの総務は、そんな未来を目指して今日も動いています。

