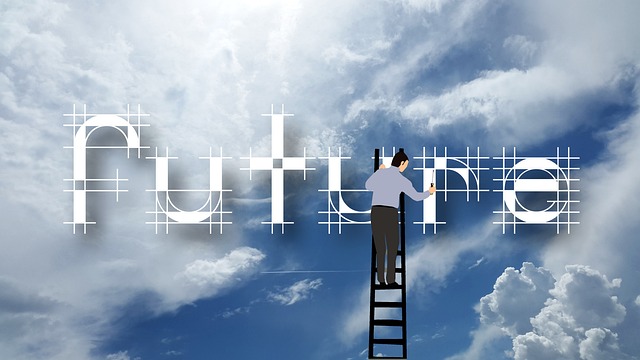
「デジタル庁への提言」とは少々大げさに聞こえるかもしれません。
しかし、デジタル化の真の目的は個別最適ではなく、全体最適によるデジタルの民主化にあります。
その観点から見ると、各企業が独自運用を進めるだけでは限界があり、国レベルでの全体最適化――つまり「まちの総務」的な視点からの提言には大きな意義があると考えています。
前回は「デジタル庁への期待」を序論として述べました。
今回はより具体的な施策として、企業間商取引の汎用化と、中小企業版JANコード化について掘り下げてみます。
企業間商取引の汎用化――“Amazon型B2B”の可能性
まずは現状整理です。
大手製造業では既に受発注システムを導入・運用していますが、地方の中小製造業ではシステム化が追いついていないケースが数多く見られます。
依然としてFAXや紙伝票に依存し、事務担当者が手入力で転記作業を行う。
納品書や請求書もExcelや紙で作成・郵送する。
このような非効率なやり取りが今なお日常的に行われています。
一方で、SaaS型の受発注システムや帳票作成サービスも登場していますが、まだ普及は限定的です。
ここで一度視点を変えましょう。
「B2Bは難しい」と捉えがちですが、B2CのAmazonをB2Bに応用する発想を持てばシンプルになります。
- 企業は製品情報を限定公開(取引先にだけ閲覧可能)
- 発注側は数量やサイズを指定して注文
- 受注側はWeb注文を基に社内展開し生産開始
- 納品書・請求書をシステムで発行し、入金まで一元管理
このような仕組みがあれば、中小製造業の取引は格段に効率化します。
実現を妨げる要因と解決の方向性
1. 取引先ごとに価格が異なる
B2Bでは顧客ごとに条件が異なるため、価格を一律公開できません。
しかし、ログイン制によって顧客別の価格設定や値引率管理を行えば解決可能です。
むしろ固定取引先との反復取引が多いB2Bでは、この仕組みが大きな効果を発揮します。
2. 商品バリエーションが多く登録が困難
「商品名・厚さ・幅・長さ」に加工条件を加えれば価格は確定可能です。
各社は既に内部で製品コードを管理しており、伝票確認に利用しています。
つまり課題は共通のコード体系をどう設計するかに絞られます。
中小企業版JANコード化――共通言語としての商品コード
ここで着目したいのがJANコードの仕組みを中小企業に応用することです。
JANコードは「どの事業者の、どの商品か」を示す国際標準コードで、スーパーのレジで「ピッ」と読み取られるあのバーコードです。
現在のJANコードの構成は以下の通りです。
- 事業者コード
- 商品アイテムコード
- チェックデジット
この枠組みを中小企業向けに拡張し、柔軟な設計で共通の商品コードとして運用できれば、B2B取引の効率は飛躍的に向上します。
運用イメージ
- 中小製造業が事業者コードを登録(工場単位も可)
- 製品名+規格条件を基にコード申請
- 備考欄に素材や加工条件を付与
- 発注企業ごとの金額(係数込み)を登録
- 受発注システムと連携して自動処理
このようにコード化が進めば、FAX文化に依存する中小企業の現場も、EDI(電子データ交換)による効率化へ自然に移行できます。
デジタル庁への期待――「最適化DXの本丸」
B2B受発注システム自体の開発は、技術的には難しくありません。
Amazonや楽天、モノタロウが既に実証済みです。
本当に難しいのは、企業間取引を支える「コード化」の標準化です。
これを一企業や民間団体に任せるのは限界があり、国や外郭団体による全体最適化が不可欠です。
だからこそ、この領域こそがデジタル庁の真価を問われる分野だと思います。
「中小企業版JANコード」の実現は、まさに最適化DXの本丸となるでしょう。
「レッツDX」

