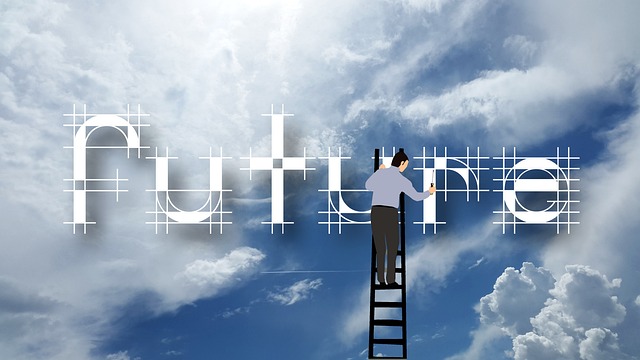
デジタル庁への提言などと大きく出てしまい恐縮ですが、あえて申し上げたいことがあります。
それは「デジタル化の目的は個別最適ではなく、全体最適を実現するための民主化」であるという点です。
各企業が独自運用を続けていては限界があります。だからこそ、「まちの総務」として現場に横串を入れながら提言する意義があると信じています。
前回は「個別会計処理の統合化」について、企業を「お客様(=税金支払者)」と捉え、なぜ個別にシステムを導入しなければならないのか――「本来は逆ではないか」という問題提起をしました。
今回はその延長線上として、「個別給与計算の統合化」に焦点を当てます。
なぜ給与計算は標準化されないのか?
「まちの総務」として多様な中小企業を支援してきましたが、共通して避けて通れない課題が「給与計算」です。
もちろん制度や就業規則は企業ごとに異なります。しかし、昭和の時代から変わらない「給与計算」という同じ作業が、なぜこれほどまでに複雑化し、標準化や自動化が進まないのでしょうか。
給与計算の本質はシンプルです。
- 基本給(時給・月給・年俸)
- 残業・休日出勤・各種手当の加算
- 社会保険・税金の控除
この流れに尽きます。
企業独自の仕組みが2~3割あるにせよ、多くの中小製造業では共通の仕組みで十分対応できるはずです。それでも各社が独自システムを導入し、人件費をかけ続けてきたのは、「給与=お金」に直結するため、担当者も従業員も慎重にならざるを得なかったからでしょう。
DXの視点で考える「給与計算」
企業側にとって選択肢は2つです。
- 個別最適にこだわり、人員不足でも従来型の給与計算を続けるか
- 汎用的な仕組みを取り入れ、効率化を図るか
現在、給与計算システムやアウトソーシングサービスは世の中に溢れています。つまり「仕組み自体はすでに確立されている」ということです。
SaaSの導入により、社会保険料や税制改正があっても自動で対応可能です。便利な環境は整っているにもかかわらず、なぜ統合化が進まないのでしょうか。
国が主導すべき「給与計算インフラ」
本来、社会保険料や税制を決めているのは国です。であれば、その制度を組み込んだ給与計算プラットフォームを国が提供してもよいのではないでしょうか。
- マイナンバーと銀行口座を紐づけ
- 給与支払いから年末調整まで自動化
この流れが実現すれば、税金の取り漏れも防げ、企業の負担も大幅に減ります。
実際に実現を阻んでいるのは「できない技術的理由」ではなく、行政内の調整不足や既存業界への配慮といった政治的要因かもしれません。だからこそ、デジタル庁にこそ期待が集まるのです。
まずは「省庁の壁」を越えることから
給与計算という全企業に共通するバックオフィス業務こそ、DXの第一優先課題であるべきです。
ただし、その実現には次の調整が欠かせません。
- 省庁間の壁を撤廃し、データを横断的に活用できる環境づくり
- SaaS事業者、社労士事務所、会計事務所への配慮
- 業界既得権益との調整
既にデジタル化の技術基盤は整っています。あとは「変革(エクスチェンジ)」に踏み出す覚悟が必要です。これはデジタル庁にしか成し得ない役割です。
給与計算DXのその先へ
統合された給与計算プラットフォームが整えば、その次にAIによる人事評価や自動判定の導入も視野に入ってきます。単なる業務効率化にとどまらず、人材マネジメントそのものを変革する可能性が広がるのです。
給与計算は企業規模を問わず全員に関わる業務です。だからこそ、ここにDXの突破口があります。
デジタル庁の本気の取り組みに期待せずにはいられません。
「レッツDX!」
シリーズ構成(進行中)
- デジタル庁に期待すること
- 企業間商取引の汎用化と中小企業版JANコード化
- 個別会計処理の統合化
- 個別給与計算の統合化 ← 今回
- 企業提出情報のDB化(紙の電子化NG)
- 番外編 SaaS情報のWebAPI連携標準化
- 番外編 情報セキュリティ管理の共通化
次回に続きます。

