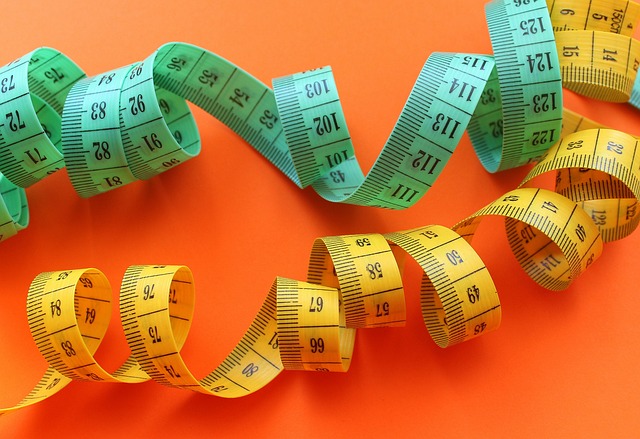
日頃、近隣企業の皆さまへITサポートを提供する中で、改めて気づかされた重要なポイントがあります。本コラムでは、いわゆる“バックオフィス業務(人事・総務・経理・IT・購買など)”における非効率の実態と、その背景を事例を交えて解説します。
同じ業務なのにバラバラな運用が存在する現実
企業規模や業種に関わらず、企業活動に必要なバックオフィス業務では、共通の成果物(アウトプット)が求められます。多少、入力情報の精度や量に違いはありますが、基本的な業務内容は同じです。
しかし、現場の業務運用を俯瞰して見ると、「同じ仕事なのに、会社ごとにまったく異なる方法で処理している」という非効率な現状が浮き彫りになります。
担当者にとっては、自社のやり方が“標準”であり、過去に教わった手順や自身の改善の積み重ねに基づいて日々業務を遂行しています。その姿勢自体は評価すべきですが、企業を横断的に見ていると、驚くほど業務の進め方がバラバラであることに気づきます。
業務マニュアル化が明らかにする“運用の差”
当社では、IT支援の一環として各社の「業務マニュアル作成支援」を行っています。その中で、各担当者に業務フローをヒアリングし、可視化を進めると、驚くほど運用方法に差があることがわかってきました。
事例:同じ業務の運用パターンの違い
- A社:手書き資料+電卓で集計
- B社:Excelに手入力し台帳を手作成
- C社:Excelマクロを活用して自動集計
- D社:SaaSを活用しクラウドで情報共有
これらは、いずれも最終的に同じ成果物を求められる業務ですが、用いている仕組みや効率性には大きな開きがあります。
差を生むのは“人力”と“仕組み化への意識”
この違いは何から生まれるのか。大きな要因は、組織のリソースと「改善を支える人材」の有無です。
- 与えられた業務をこなすだけで手一杯
- 日常業務が多忙で改善に時間を割けない
- 周囲に改善を支援できるスキル人材がいない
- 自ら進んで仕組み化する意識や能力の差
つまり、言い換えれば「スーパー事務員」の存在がカギなのです。
これは地方自治体にも似た構図が見られます。予算や人員によって、同じ業務でもデジタル化が進んだ自治体と、従来のやり方を続ける自治体で、業務効率に大きな差が出ています。
標準化の妨げになる「先進事例の孤立」
現在、行政の世界では“デジタル庁”のように、全国的な横断組織が設けられ、共通の業務基盤づくりが進められています。しかし、ここでも課題が浮かび上がっています。それは、先進的にデジタル化を進めた自治体ほど、標準化への歩み寄りが難しいという事実です。
既存の独自システムが足かせとなり、かえって非効率化してしまうケースも見られます。これは、民間企業にもまったく同じ構図が当てはまります。
「まちの総務」が果たす役割
中小企業においても、同じ業務なのに各社でバラバラの運用が行われている。これは、企業間での効率性に差が出る大きな原因です。行政のような強制力は働きませんが、だからこそ「まちの総務」のような中立的な立場からの支援が求められています。
【第一ステップ】仕組みを“見える化”し、現場にあった最適化を
まず取り組むべきは、以下のステップです。
- 業務内容をフラットに確認し、現場にとってのベストプラクティスを導き出す
- 費用や工数を最小限に抑えつつ、各社に適した仕組みを導入する
導入候補としては以下のような選択肢があります。
- Excelマクロ(VBA)による自動処理
- RPA(業務自動化ツール)の活用
- kintoneなどノーコードツールの導入
属人化を防ぐ“横展開”の重要性
ExcelマクロやRPAには、開発者しかメンテナンスできない“属人化”のリスクがありますが、良い仕組みを複数社で共有・展開していくことで、この問題は大きく軽減できます。
必要であれば、マニュアルや仕様書の作成など、当社が実務レベルでの支援を行います。
次回予告:標準化された仕組みを“どう広げるか?”
仕組みの標準化が実現できれば、大きな前進です。次に考えるべきは、
どうやってより多くの企業に広げていくか?
この点について、次回のコラムで掘り下げていきます。

